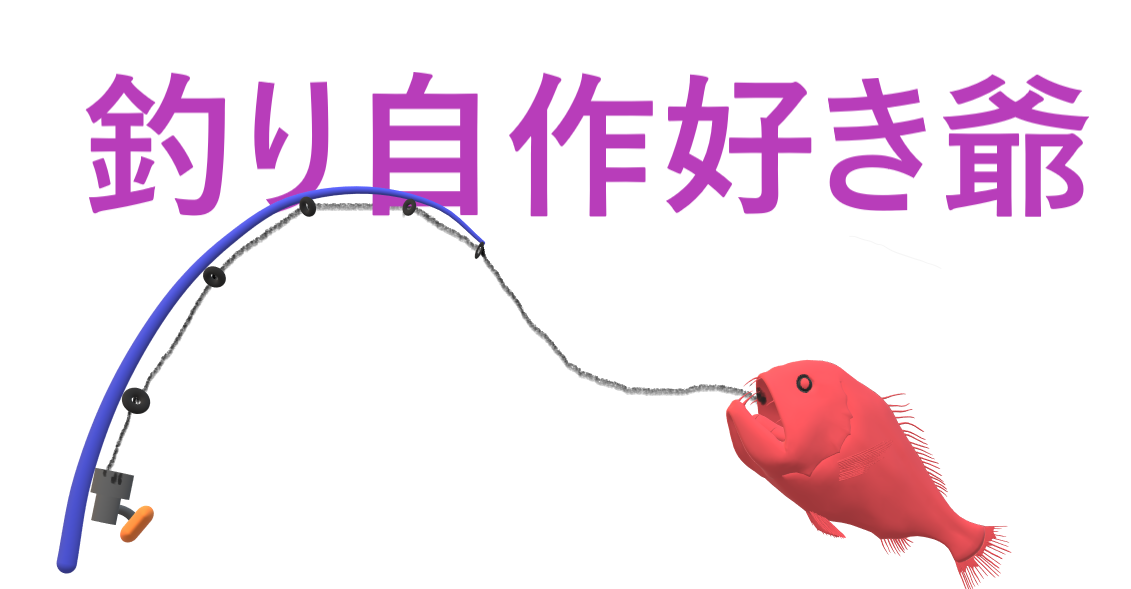極小円定規の活用方法(かや7)
かやウキ作りで必要な工具道具は色々ありますが、必要最小限で持っていた方がよい道具、工具、資材は薄刃のカッターナイフ、紙ヤスリ、マスキングテープに極小円定規に小さ目のノギス、精密ヤスリ等ですが、今回は私の極小円定規の活用方法を説明します。
極小円定規はウキ作りでは必須アイテム
かやを正確に等分して縦の切れ込みを入れていくのは難しい作業ですが、これが上手くしないと歪な形のウキになります。私はこの作業では極小円定規を使っています。

ステッドラー社の極小円定規(97622)はかやウキ作りでは必須アイテムです。

購入後の前作業として径が6mmから8mmの円の淵の外側に分度器で60度間隔の箇所にカッターナイフで定規の裏面に薄く切れ込みを入れていきます。定規の横線と分度器の線を正確に合わせて位置決めをしてください。これは正確に行います。写真では7mmの箇所が分かり易いかと思います。
1.かやの径、太さの確認
かやウキを作る時は、まず、かやの径を確認しますが、この時に役つのはこの定規です。かやの径はノギスでも計測できるのですが、円形定規でもできます。

写真の様にかやの上部の径を確認します。なお、海上釣堀でかやウキを作る時は、かや径のサイズは中(7mm)か太は必要です。ただ、かやの極太(10mm以上)は非常に成型が難しいのでお勧めはしません。

かやの中間部も計測します。かやウキをつくるときは、かやの径が太い方を上部にしています。
2.縦割りの印付け
海上釣堀用のかやウキ作りではかの径は6mmから10mmまで程度が良いのですが、径が大きくなると分割数は増えては6分割から8分割と必要になってきます。また、径が小さい場合や切れ込みの寸法が長いと分割数は少なく出来ます。なお、径が大きいのに分割数が少ないと絞り込みが難しくなったり形状が悪くなります。では、定規の活用方法を説明していきます。

定規の表面からかやを差し込んで印にマーカーペンでかやに印を入れます。4分割なら定規の印に沿って入れます。8分割なら定規の印を使って目分量で、なお、円定規にかやを差し込む前にかやを真円状にしますが、かやが楕円状だと均等に分割されません。かやの楕円の解消方法はガラス絞り器等を使いますが、無い場合はアイロン等で成型しても良いかと思います。

事前に割れを防ぐためにかやの下部にマスキングテープを貼ってから、かやに入れた印の箇所にカッターナイフを入れて手前と前に少しずつ切り込んでいきます。切れ込みの深さはかやの上部だと2cmから4cm程度で下部は4cmから8cm程度です。
3.成型(合わせ目)の確認
かやの成型時に上手く成型出来ているかの確認を行うのですが、私はこの確認の時に円定規を使います。

カットしたカヤを何個所かの定規の穴にさしこんでかやの合わせ目を確認していきます。この写真だとかやの綿が余分に出ているようなので、補正していきます。補正方法は紙ヤスリで削っていきます。

かやの先を指でつまんで合わせ目の確認をしていくと良いかと思います。かやの綿を削り過ぎないもの重要です。
4.接手部の仕上に
かやの上部や下部に芯材となるソリッド等を差し込む作業がありますがかやの絞り込みの径を正しくしないと芯材がぐらつくことや美観上の問題が出てきます。これを防ぐために私は円定規を使っています。

芯材となるソリッドの径が2mmの場合は1.9mmから2mm程度までかやの先端を成型して絞り込んでいきます。ただ、いきなりはこの径には成型は出来ませんので、かやを削って成型しながらこの径にしていきます。

かやの先端は余分な綿は取り除いて外皮のみにしていきます。綿を取り除く方法は精密ヤスリの半丸か丸を使います。写真の様に定規の2mm程度の穴の箇所に差し込んだかやに精密ヤスリを差し込んで綿を取り除いて外皮のみにしていきます。この時にかやに段差が出ていれば平ヤスリなどで補正していきます。

かやを外皮のみにしても、どうしてもソリッドの接合部は段差がでます。段差を無くして均一にしたい場合はソリッドの挿入個所部の径を削って細くして段差を着けていけば接合部の段差は解消されます。ソリッドを削る作業は手間はかかります。

写真をみると段差はあまり解消されていません。ソリッドの加工の手間を惜しんでいたか、なお、この後かやの下部の接手箇所は強い衝撃を受けるので糸巻での補強は行います。

円形定規等を使ってかやを成型し終えました。成型の完了はこんな感じです。私の場合は一本あたりの作業時間は成型では3時間以上は要します。
5.終わりに
とにかくかやウキ作りは手間、時間がかかります。手を抜けば良い物は出来ません。多くの失敗の経験も必要です。