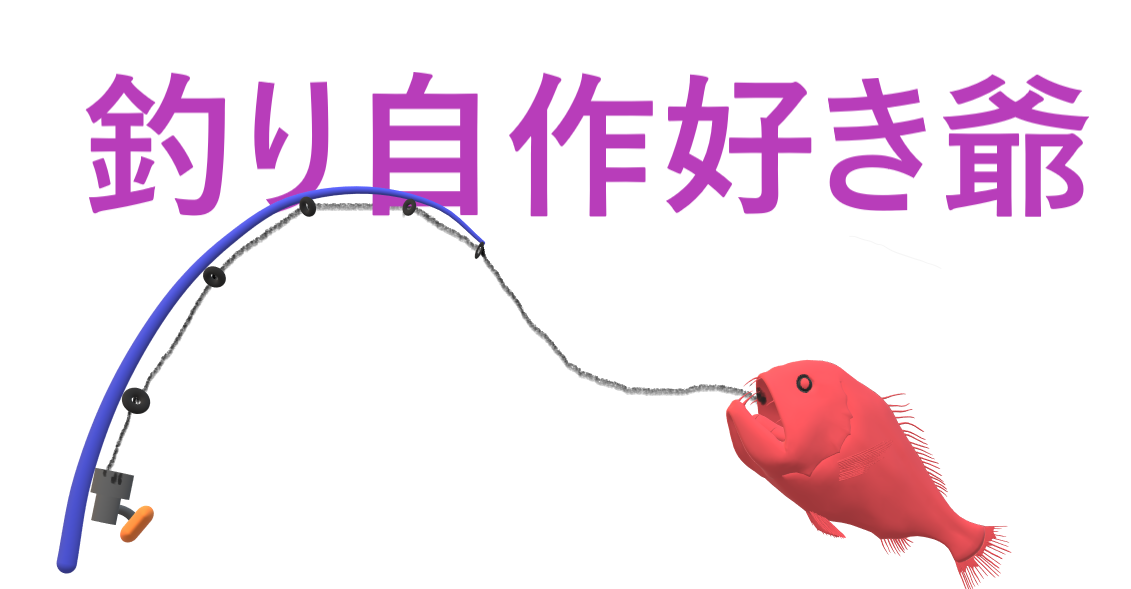かやウキの自作キットを売ってみる。
自作で作ったかやウキをネットで売ってみましたが買っていただけなかったので、今回はかやウキの自作キットを売ってみることにしました。自作キットですが、かやのカットや芯出しなど難しいところは私が行っています。購入者さんにお願いするのは、接着、かやの塗装等の作業ですが、この作業もかなり難しいところはありまあす。売り値は2本セットで1,400円程度を考えていますが、この自作キットを作るのに述べ4日以上の時間を費やしました。塗装は塗り過ぎないで丁寧に仕上げれば、非常に感度の良いお気に入りのウキになるかと思います。ただ、自作キット用の作成は時間もかかるので数セットしか売ることはできません。なお、へらウキのトップの仕様に近いですが塗装は済ませています。

この自作キットをかやウキ2本をネット販売してみることにします。この他に紙やすり400番と耐水ヤスリ1000番も必要分を同封します。

かやのカット、成型は私がしています。いつもより丁寧に仕上げています。合わせ目はほとんど目立たないかと思います。

私のカット成型の例です。合わせ目の一番目立つ箇所を撮影しています。一番下は合わせの失敗の例です。たまに失敗します。今回は成型に相当時間をかけたので失敗されることは少ないかと思います。

自作キットが完成したらこんなウキになります。なお、一番下のウキは青物用のウキですが今回は関係はありません。1号から2号のウキの予定です。多分、完成したら一番お気に入りのウキになるかと思います。
なお、このページはかやのカット成型以降の作業工程の説明です。かやのカット成型までの説明はまた別の機会に投稿していきます。
自作キットで必要な材料、工具は
必要な材料、工具は
1.塗料(ウキのボディ部用は漆か二液ウレタン等)、アクリル絵具、筆、木綿糸、両面テープ、接着剤

この二液ウレタンが良いのですが、空気の流れのあるところで塗装しないと非常に気分が悪くなります。お勧めはしません。毒性があるのではと認識して作業を進めると良いかと思います。コスト的にはウキの塗装用の漆と漆薄め液のセット方が良いかと思います。

コニシボンドのEセットが15gが良いかと思います。接着剤の硬化は時間がかかりますが、その分良い点もあります。
作業工程は
1.仮の糸巻をする。
この仮巻き作業はかやの切れ込み部に木綿糸で糸巻をして合わせ目の確認を行い芯のセンター取り作業(ブレの是正)をしていきます。また、仮巻きの状態で二、三日置くとかやを馴染ませまることができます。この糸巻は接着をする前の練習にもなります。接着は仮巻きの時には行いません。

1.かやの表面は油分があるので糸巻時に滑るので、紙やすりで軽くこすって油分を取り除き巻きやすくします。

2.かやの上部は角度があるので糸巻が難しくなります。このため両面テープを先端部に巻きます。

3.木綿糸で仮巻きをするのですが、この時はかやの先端からでなく中央部から尖端部まで巻いていきます。この時、仮巻きですが、かやの切れ込み部が段差がでないように巻いていきます。また、芯材も挟み込んで糸巻をします。

4.ウキの上部の仮巻きなら芯材にウキのトップを軽く差し込んで写真の様に平らな所で転がしてみます。この時に芯材にぶれがあるようでしたら軽く芯材の角度を直していきます。この時にトップの接着は行いません。

5.同じようにかやの下部も仮の糸巻をして、貼り合わせと芯材のぶれの確認をしていきますが、切れ込みの角度が急でないので両面テープの貼り付けは必要はないかと思います。なお、ソリッドはテーパー加工をしてかやの本体に負担がかからないようしています。これも時間を相当要しますが、見栄えも良くなります。

6.かやのカットがきつい時は先端部は糸が滑るので上手く巻けません。このため糸巻の要領として、カット箇所の根本付近(親指付近)では一回と少しぐらいはかやと垂直方向に巻いてから一気に先端部まで糸を持って行き切り口が開いているかやを少し締めてまた糸を根付近までもっていきます。これを八の字巻きいうのか、これを何回も繰り返すとカットのきついかやでも、徐々に切り口がふさがってきます。
2.接着作業を行なう。

8.かやに巻いた仮の糸巻をほどいて両面テープを貼っているならテープかすが残らないよに綺麗にはがします。次に接着剤をかやの切れ込み箇所に着けていくのですが、私は不要になった両面テープの剥離紙を使います。この剥離紙は薄くて接着剤も着けやすく、かやの切れ込み部の奥の方まで剥離紙が入り込むので接着剤も切れ込み箇所の奥深くまで届きます。

9.接着剤のEボンドはA剤とB剤の2液を混ぜるのですが、私は爪楊枝で2本を用意して、1本はA剤用でもう1本はB剤用としてチューブから取り出してよく爪楊枝で混ぜあ合わせています。量的にはそれぞれ1円玉から5円玉ぐらいの量で良いかと思います。よく混ぜ合わせてください。強度が出ません。

9.なお、薄い刃のカッターナイフを接着用具として使ったこともありましたが、両面テープの剥離紙の方がよいと思います。どちらでも構いません。

10.接着剤を塗り終えると次に先端部も仮巻きと同じ要領で糸を巻きあげていきます。この時、両面テープは使いませんので八の字巻きのみで切れ込み箇所を締めていき、切れ込み箇所の隙間を無くしていき段差も出ないようにします。段差がでるようでしたら巻き直しをしてもいいです。なおソリッドは先が細い方をかやに挟み込みます。また、糸巻時に接着剤が多くはみ出ている時はぬぐい取ります。また芯材のぶれも確認します。

11.この接着剤は硬化するのに時間を要しますので、これを利用して接着後一時間後ぐらいにもう一度芯材のぶれを直すことが出来ます。この時にぶれがあるようでしたら補正していきます。なお、ウキのトップは接着しません。

12.足部も先端部と同じ要領で接着を行ないます。糸巻が終わると、硬化時間は最低は丸一日以上は要しますので、目安としては2日間程度を硬化に時間を割きます。なお糸巻の不具合などで接着不良で隙間があいてしまうことがありますがこの場合は隙間に接着剤を差し入れても一度、糸巻をすると上手く行くかと思います。

13.かやの接着後二日目以降に糸を解いていきますが、接着箇所の合わせ目は角張っていますので、この角を取っていく方法として、丸みを帯びた金属を使います。私はカッターナイフの刃受け部を角取りによく使います。これを角張っている箇所に擦り付けて丸みをつけていきます。あまり強く擦ると合わせ目が割ける恐れがありますので加減をみて

14.かやの角張っているところを直しますと、次にカヤを400番の紙やすりでカヤ全体を磨いていきます。先端部は紙やすりを回すようにして磨いていき、中央部は縦に擦って磨いていきます。この時、太いかやなどは筋も目立って荒いのでこの時磨いて無くしていきます。ただし磨きすぎると中綿がみえることがあるのでそこそこで止めておきます。

15.かやの最下部の箇所は合わせ時に衝撃を強く受けるので、口が割れてくることがあります。このため写真の様に細い糸でかやの先端部を糸巻して補強します。巻く量は先端の2ミリ程度で良いかと思います。写真の様に多く巻く必要はありません。なお、糸は瞬間接着剤でほどけないように接着しています。
3.かやウキを塗装する。
ウキに名を入れる。
ウキの名を入れると、ウキの値打ちが間違いなしに上がると思います。また、より愛着も、名は自分の好きな文字を選んで書き込んでください。ただ、手書きだと用紙等に何度か書き込んで練習してからですが、字画数が多いと難しいです。他にはデカールシールの場合はシールを購入してパソコンに文字を作成して、文字の反転印刷を指定してプリンター印刷をします。デカールシールの場合は==>デカールシール のページを参照してください。

ウキに名を入れる方法はまず、水性のアクリル絵具等で筆で手書きする方法があります。手書きは難しいですがデカールシールより気に入っています。なお、名を「八天」したのは画数も少なく書きやすいためです。

デカールシールでウキに入れる方法もあります。パソコンで指定して反転印刷で名を印刷します。当然ですがデカールシールなら画数は多くても問題はありません。
4.うきを塗装する。
私は塗装は下手で苦手です。が一応説明します。これが上手く行けば、本当にいいウキになります。

ウキの着色が決まっていないなら私は写真の様に水性のアクリル絵具でこま塗をお勧めします。かやの着色は上部は湾曲箇所のみで、下部はかやの下部数センチの所から一番下までウキのカンまでで、中央はかやの素材の色を生かして着色はしません。着色は重量も増えます。この塗りかたは簡単で飽きが来ません。なお、着色をしない方法もあります。この場合はかやの切れ目を目立たないよう隠していくのが重要です。

こま塗の方法ですが、段ボールの箱の上を写真の様に三角にカットしますと置かれたウキが位置ずれを起こしませんので綺麗に塗装できるかと思います。ただ、このままだとウキは左右には移動しませんが上下には移動するので、箱の蓋をテープで貼って上下の移動を止めます。この状態で着色の際にウキを回転させてながら塗装すれば良いかと思います。

ウキの塗装は空気の流れのあるところでしています。私は扇風機を2台(入りと出し用)を使って窓際で塗装しています。塗装の基本は薄く塗る。2液ウレタン液にさらに薄め液を20%以上を加えています。漆でも薄め液を入れて薄めます。これを3回以上を乾燥させては薄く塗って塗装をしていきます。なお、雨天は湿気で塗料が白濁するので行いません。

今はかやの乾燥の方法はウキが立つよう木材に穴を開けてその個所にウキを差し込んで乾燥させています。クリップでソリッドを挟んで糸で吊るして乾燥させる方法もあります。
塗装後、2,3日開けて十分に硬化させてから、1000番程度の耐水ペーパーで水を付けて磨き表面を軽く磨きます。そのあと研磨用のコンパウンド(車両用でも可)でこれを布などにつけて、ボディーと足を磨いて光沢を出していきます。いい写真がありません。
5.トップを装着する。
いよいよ完成間近になります。ウキのトップの装着を一番最後にするのは、製作過程でトップに汚れが付きやすいからです。特にあらかじめトップに蛍光塗料を塗っている時は最後の工程になります。

まず、トップの接着の前にウキの上部のソリッドにウキのトップを付近まで差し込みます。そして、まだ接着していないのでトップを少しずつねじって一番ブレの少ない箇所を見つけていきます。その個所に養正テープ等を利用して目印をつけます。というのもかやも多少は湾曲していて、ウキのトップも多少湾曲しています。この癖を利用して一番ブレの少ない個所が出てきます。この箇所がトップを接着する箇所になります。また、トップが長いと思われる方は少しカットして短くしてもかまいません。

この作業が終えると最後の工程、トップの接着ですが接着の方法はEボンドで接着していきます。なお、ソリッドの径とトップの内径を合わせているため、瞬間接着剤でも問題はないかと思います。また、接着箇所は一番根本付近のみで良いかと思います。ソリッド全体に接着剤を着ける必要はないかと思います。この理由はトップが折れた時に新しいものに付け替えやすいからです。
何処のサイトで出すの
出品はネコポス用の箱が家にあるのでメルカリに出品します。3セット分は作りましたので、とりあえず3セット分の自作キットを出品しますが、出品開始は12月1日からの予定ですが、多分買っていただけないかと思います。
補足:キット1セット分買っていただけました。驚きました。今は評価待ちです。なお、かやウキは非常に軽いので感度は良いかと思いますが、目に見えて釣果がアップする訳ではありません。特に鯛釣りの場合はどんなウキでもそれなりに釣れるのでウキの感度はほとんど影響しません。ただ、ウキの感度が求められるシマアジは魚に軽いため違和感を与えないので幾分釣果アップになるかもしれません。

餌が着いていない空針時でトップ位置をこの位にをおもりで調整をしておくと、団子等の餌だと一節から二節程度沈みます。餌が無くなるとこの位置に戻りますので、餌の交換のタイミングが分かり時間の無駄が無くなります。

水性のアクリル絵具で自分の好きな色を塗ります。デカールシールで名前入れもしています。